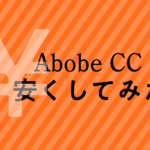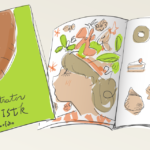イラストレーターがどうやって仕事を取るか。人によって、仕事内容によって、またジャンルによって最適解は違うでしょう。
でも、仕事の取り方ってある程度セオリーがあります。ここではどのイラストレーターでも共通しそうな手法と考え方を説明します。
まず考えるべきこと 1 : どういう仕事をしたいか
「どうやって仕事を取るか」を考える前に、絶対に考えておくべきことがふたつあります。
ひとつめは「どういう仕事をしたいか」。
イラストレーターとひとことで言っても、描くものは人によってさまざまです。絵柄のジャンルもあります。
ということは、その絵がどんな仕事に向いているか、も人それぞれってことです。
あなたの好きなジャンルがイラストの全てではないんです。自分ではなんとなくわかっていたとしても、それを他人にわかりやすく説明できるようにしておきます。
まず考えるべきこと 2 : 戦略
ふたつめに考えることは「戦略や作戦」です。仕事を取るために何が必要なのか、その理屈を勉強して知ったり自分で考えたりすることです。
イラストレーターはよく「お仕事をもらう」という言い方をします。何気なく言っているだけではあるんでしょうけど、仕事は「もらう」もんではないです。
「もらう」っていうと、下手に出てお願いをしてなんとか恵んでもらう、というイメージですけど、ひたすらに「お仕事ください」ってお願いすれば必ずもらえるわけじゃありません。
そうじゃなくて、正解は「私に頼んでくれたらこういうメリットがあるから取引しませんか?」です。自分のスキルがどこで必要とされているか知って、どうやって届けたらいいか? を考えます。
そして仕事はいきなりは発生しないので、ある程度長い期間での行動が必要です。
仕事を「取る」といいますけど、山のどっかにある果物を偶然見つけて取ってくるのとは違います。それよりは、自分の庭に苗を植えて育てて収穫するイメージのほうが正しいです。
どの媒体? どんな企画?
どういうところで自分のイラストが活かせるかをだいたい把握するには、どんな「媒体」と「企画」にマッチするかを考えることです。
イラストの仕事というのは、何かに掲載されてはじめて仕事になります。この掲載される何かを「メディア」または「媒体」といいます。
イラストレーターの仕事で中心なのは、出版です。書籍、雑誌、ムック、絵本、教科書など。次に多いのは広告とウェブサイトでしょうか。
その本やウェブサイトがどんなテーマを扱っているか、が「企画」です。
あなたの身の回りで、どういうところにイラストが使われていますか? わからない人は調べてみてください。その中で「こういう仕事がしてみたい」と思えるものはどれですか?
それがわかると、どこの誰に知ってもらうべきかがわかります。
イラストレーターの仕事 = 企業との取引
イラストレーターの仕事は企業間取引、いわゆるB to Bです。
イラストの仕事は、一般人を相手にする商売とは特性が違います。
一般人相手の商売というのは例えば、Amazonでお米を売っているとか、ドラッグストアで化粧品を売っているというようなことです。そういう商売では、「パッと見ていい感じの広告」や「思わず買いたくなってしまう安さやサービス」が有効です。
でも、イラストレーターは、そういうことをしても仕事には結びつきません。必要なのは「時間をかけてじっくりと検討してもらうこと」「信用を築くこと」です。それが「特性が違う」という意味です。
反発を覚える人もいるかもしれません。「いやいや、個人からのアイコン依頼とかも私は受け付けているよ」と。でも、ずっとイラストレーターとしてやっていくつもりならそれだけでは厳しいので、いずれ企業との取引を始めなければならない時が、必ずきます。
仕事を取る方法 1: SNS
SNSのアカウントはひとまずひととおり作っておくといいでしょう。Twitter、Facebook、LinkedIn、あとSNSとは若干違うけどAdobeのBehance(ビハンス)も。
ただしTwitterは、仕事を取るための活用方法はじつはかなり難しいので注意が必要です。
バズっても仕事依頼は増えないと思っておいたほうがいいです。
なぜなら、イラストを発注する企業の中の人が、「バズってるから」を理由に発注先を決めることはないから。前述のように「イラストの仕事は、一般人を相手にする商売とは特性が違う」ってことです。
こういう特性をふまえて、使い方を考えなければなりません。イラストレーターになりたい人とか同業者とばかり交流したところで仕事が発生するわけありませんのでね。
仕事を取る方法 2: クラウドソーシングサイト
クラウドソーシングサイトが仕事の依頼をゲットするのに有効という人もいます。ただ、私はおすすめしません。多くのフリーランサーが言っているように搾取の温床でもあるからです。
でも、全く実績のない人にはチャンスの場のひとつにはなると思います(そのうち脱却したほうがいいけど)。仕事のスパンも短いことが多いみたいなので、比較的すぐお金になるのはメリットかも。
やるなら1対1の受注のみに絞ること。募集を見てデザイン画像を投稿する「コンペ形式」だけは手を出すべきではありません。
仕事を取る方法 3: 外注募集に応募する
出版社や制作会社が「外注パートナー募集」をウェブサイトに掲載している場合があります。これを探して応募するという方法。
心理的な負担は少ないし、実績がある人なら実りやすいので、やって損はない方法ではあります。
ただ、応募したからといってすぐに仕事依頼が発生することはほとんどありません。あくまで知ってもらうためのきっかけと考えたほうがいいです。
仕事を取る方法 4: 直接営業
あまりやりたくない人が多そうですけど、直接営業するのは今でも有効な方法のひとつです。ただ、いきなり直接訪問するのはナシです。まずは電話。メールでもいいですがスルーされる確率がかなり高いので電話がいいですね。
人手の足りてない制作会社など、案外営業が歓迎される場合もありますよ。
大手出版社は最近は売り込みお断りのところが増えてますが、全てがそうではないので完全にあきらめるべきではない。
意外と、まだ実績がない人におすすめの方法って思います。なぜなら、最初の実績がクラウドソーシングだと何かと舐められるけど、最初の実績が自力で営業して依頼された仕事だったら、次からの営業が格段にやりやすくなるから。イラストレーターのキャリアとしてすごく強いものが築けます。
仕事を取る方法 5: 交流会
異業種交流会やクリエイター系交流会、セミナーなどに顔を出してみるという方法。確実では決してないけど、仕事のチャンスに巡り会えることはあります。
ただ、仕事を得る手段として考えているとデメリットが大きいので、メインはあくまで交流や学びであって、その中でチャンスがあればいいかな……くらいのスタンスでいるほうがよい。
デメリットっていうのは、搾取に合う可能性が高いこと。「仕事を求めて交流会に来るクリエイターなんてどうせ仕事がない奴なので、格安でこき使っても良い」と考えている人がけっこう存在します。
仕事を取る方法 6: 商談会
有名なのはクリエイターEXPOですね。これは交流会でもアートイベントでもなく、商談会です。
現実に出版社や制作会社の人が訪れるので、直後から仕事依頼が発生することも十分あります。
ただデメリットとしては出展費用が高いこと。それでも十分モトは取れるのですが。あと、アートイベントやお祭り感覚で出展しても実りは少ないので、やり方を考える必要がある。
ところで交流会や商談会に行くのだったら、「ちゃんとした」名刺を作っておきましょう。おしゃれなトレーディングカードみたいなやつじゃなくて、ビジネス用途のものを。本名も住所もちゃんと記載しましょう。
仕事を取る方法 7: ウェブサイト(ポートフォリオサイト / イラストサイト)
どんなキャリア段階のイラストレーターにもおすすめなのがこの方法です。ウェブサイト、いわゆるポートフォリオサイトを作って活用して仕事を取る。
しかも、ここまでに挙げた「仕事を取る方法」のどれもが、ポートフォリオサイトと組み合わせることでより効果を発揮するという。
- Twitterだけでは仕事依頼は発生しないので、ポートフォリオサイトのURLを載せておいて「興味のある方はじっくり検討してください」と誘導する。
- 営業や外注募集の応募のときに「詳しくはウェブサイトをご覧ください」と案内することで効率が上がる。
- 名刺にURLを載せておくことで、その場で話す時間が少なかったとしても後から実績を知ってもらうのに役立つ。
お得でしょ? なので、ポートフォリオサイトは作るべきです。
ただ、デメリットもあります。それは、ある程度技術的な知識が要求されることと、完成までかなりの手間がかかること。あと、正しい作り方・使い方を知らないとその手間がムダになってしまうこと。
「ポートフォリオサイトなんか作っても仕事依頼は来ないでしょ?」って思っている人。そのとおりで、クリエイターのみんなが大好きな見た目重視オシャレウェブサイトでは、仕事依頼が来ないです。
でもビジネスを見据えてちゃんと作ると全然違います。自分では大した動きもしてないのに仕事の依頼が来るようになります。
作り方については長くなるのでこちらを読んでください。
いしつく!の教科書|いしつく! / イラストサイトのつくりかた|note
仕事を取るのにあまり効果的ではないこと
最後に、よくイラストレーターが「仕事を増やすのにこれをやるといい」って言っているけど微妙なこと、をふたつ挙げます。
ストックイラストに投稿する
これは頑張れば放っておいても収入になるのでその意味では素敵なんですが、仕事依頼を増やす効果はないと思ったほうがいいです。
ストックイラストを買う人は依頼という面倒な行為をしたくないから購入するんであって、依頼には結びつきにくくて当然です。
また、ストックイラストでいくら売れようと「イラスト制作を依頼された」という実績が増えるわけではないので、そればかりやっているといつまで経っても実績が積めないことになります。
知り合いのツテを頼る
これもよくいう方法ではありますが、ミスマッチの温床でもあるので、やるなとは言いませんが、メインに据えることではありません。
仕事を「知り合いからの紹介」に頼るな。強みを作れ。そしてポートフォリオサイトを作れ。[イラストレーター/フリーランス]|いしつく! / イラストサイトのつくりかた|note
いわゆる「知り合い」や「人脈」の輪を飛び越えた外の世界に、自分の強みやできることを表明していくことを厭わないでほしいです。
そこへ行くと、ポートフォリオサイトを窓口にして来る仕事は、自分の人脈など全く関係のないところから来たりします。純粋に実績や特性を期待されて依頼されるわけですね。だからツテよりも条件のいい仕事が多いです。
いしつく!の教科書
「ポートフォリオサイトで仕事依頼が来るって、ほんとにそんなこと可能なの?」
そんなイラストレーターに読んでほしい全5章のnoteマガジンです。専門用語はできるだけ使わずに書きました。
目次 & 概要
-
まえがき 9割のイラストサイトは仕事の役に立っていない
そもそもウェブサイトを仕事に役立てること自体が無理なのでは?そう思っているかたに、私の体験をお話しします。まえがきを読む » -
第1章 イラストサイトに仕事の問い合わせが来ないのは、こんな勘違いをしているから
「作品ギャラリー」を作ろうとしたり、ウェブサイトなんか活用できないものと思い込んでいたり。よくある勘違いを挙げました。1章を読む » -
第2章 仕事の取れるイラストサイトを作るための、正しい作戦
どう作り、どう利用していくべきか、という全体の作戦をお伝えします。いちばん大切なのは、信頼を得ること。バズや過剰なアクセス稼ぎは要りません。2章を読む » -
第3章 仕事の取れるイラストサイトを作るためには、こんな材料をそろえよう
ドメインやサーバー、コンテンツの用意のしかたを解説します。プロフィール文の改善例や、イラスト画像の準備のポイントなど。3章を読む » -
第4章 仕事の取れるイラストサイト、レイアウトの正解例
実際に運営されているウェブサイトのレイアウトとページ構成を解説します。なぜそのようになっているのか、デザインには理由があります。4章を読む » -
第5章 作ったあとどうする?上手な活用とは
ウェブサイトは作って終わりではありません。SEOについて、ブログのやりかた、営業メールの送りかた、現実の営業に活かしていく方法など。5章を読む »